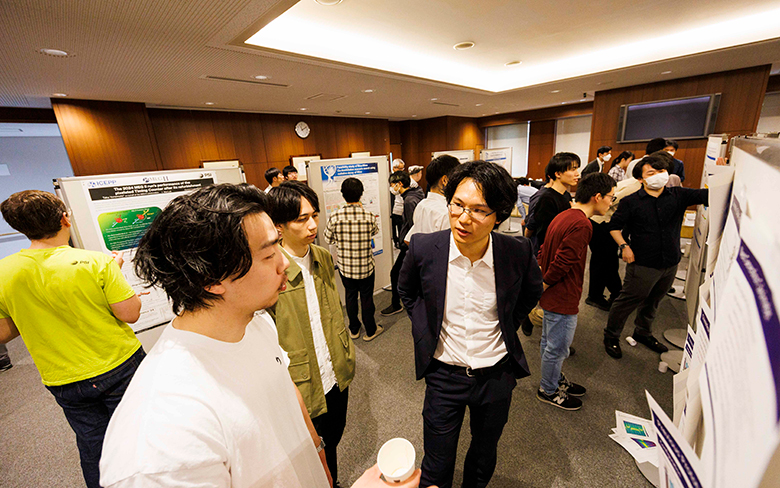
昨年に続いて二回目となる「ICEPPポスター発表会」を3月28日に小柴ホールで開催しました。
ICEPPでは複数の最先端プロジェクトを国内外で並行して進めており、うっかりすると我々の日常は自身の研究プロジェクトに没入した状態になりがちです。しかしながら「すぐ近くに面白い物理・技術があるのに互いにそれを知らないのはもったいない。研究者間の交流を加速することで新しい発想・アイデアが生まれるかもしれないし、そもそも互いのやっていることを深く知れれば純粋に楽しいはず!」という期待のもと、今年も若手研究者3人が世話人となってオーガナイズしました。
その目的のため、普段は海外の研究拠点に常駐しているスタッフ・学生が日本物理学会2025年春季大会などにあわせて多く一時帰国していることや、物理学会での成果発表の内容を負担なくそのままポスターとして発表できることから、学会直後の3月28日に開催日を設定しました。

昨年の評判も後押しし、企画の狙い通り、修士課程1年から若手スタッフまで総勢28人のポスター発表があり、およそ60人が参加する大盛況な会となりました。そのためセッションは時間配分を考慮して2部構成(1部ごとに14人が発表)としましたが、各ポスターの前では1人対2~3人ではなく1人対5~8人にも及ぶ活発な議論が展開され、セッション交代の声が会場の隅々までは届かないほどでした。実験は違えど「物理」や「検出器技術」といった共通言語で話題が広がったり、量子研究の新しいアプローチに互いの知的好奇心を刺激し合ったりと、個々のプロジェクトや研究室の垣根を超えた人の交流や研究の芽を探し出す貴重な時間となりました。
ICEPPの多くのメンバーが一堂に集まり、英知を結集して直接議論ができる機会は非常に貴重であり、来年以降も開催していくつもりです。

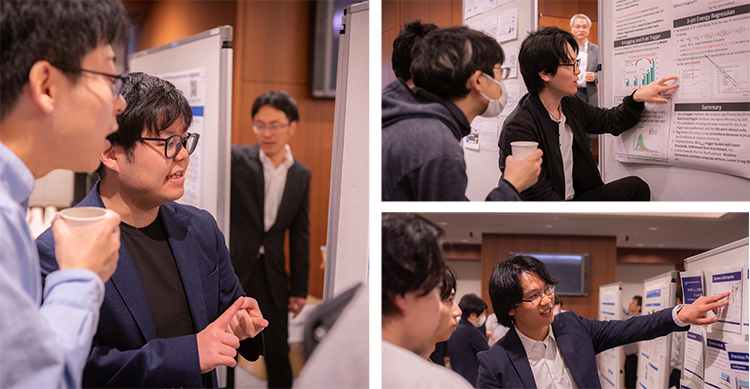
| Session1 | 近藤 翔太 “A comprehensive real-machine setup test of the new TGC Muon trigger system for the ATLAS experiment at HL-LHC.” 古川 真林 “Background Study of Long-Lived Stau Search using the LAr Time Information” 山下 恵理香 “Feasibility study of stau search for low mass splitting by leptonic-leptonic decay mode at the LHC-ATLAS experiment” 水落 永遠 “高輝度 LHC-ATLAS 実験のための TGC 検出器新型後段回路試作機におけるクロック分配と高速通信の性能評価” 西村 ダニエル “ATLAS LAr Calorimeter Digital Trigger: Firmware development with HLS for low energy events in heavy-ion collisions” 青木 匠 “Search for cascade decays of charged sleptons and sneutrinos in final states with three leptons and missing transverse momentum in pp collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector” 清野 拓己 “ヒッグスファクトリー用高精細シンチレータカロリメータのための新しい検出層デザインの開発” 山本 健介 “MEG II実験2021・2022年データを用いた最高感度でのμ→eγ探策” 森永 真央 “ジ.-ジェットに潜む言語について-” 小泉 勇樹 “Faster Quantum Algorithm for Multiple Observables Estimation in Fermionic Problems” 駒田 洲 “Sparse Pauli Channel learning utilizing n-representability” 加地 俊瑛 “Development of the initial-state dependent optimizer for quantum circuit” 神谷 好郎 “Development of Two-Dimensional Neutron Imager with a Sandwich Configuration” 林 雄一郎 “Application of Gaussian Process Regression technique to Low-mass Dimuon Resonance Search at the LHC-ATLAS experiment” |
| Session2 | 飯澤 知弥 “High Mass Drell Yan pp→ττ, γγ→ττ Analysis for τ g-2” 藏 嘉琦 “Sensitivity estimation of the leptoquark search in taunu+b final state at the LHC-ATLAS experiment” 大坪 航 “HL-LHC ATLAS TGC前段回路のQAQCにおけるデータ管理システムの開発” 張 元豪 “Advanced Methods for Non-resonant HH→bbττ Search at LHC-ATLAS Experiment with a focus on b-jet” 長坂 錬 “Feasibility study of Bino-Wino Co-Annihilation scenario search using radiative decay of Wino” 田上 理沙子 “ATLAS実験におけるヒグシーノ探索の感度上昇に向けたCalotagged-muonを用いた低エネルギーミューオンの再構成効率の向上” 田中 碧人 “Measurements of the Higgs boson production associated with a Z/W boson in the decay channel to b-quarks using pp collisions at √s = 13 TeV” 牧田 藍瑠 “Development of the muon trigger logic for the ATLAS experiment at the HL-LHC -Construction of the verification system and evaluation of the trigger performance-” 李 維遠 “RPC型チェレンコフ検出器プロトタイプのビームテストの結果” 馬越 隆成 “MEG II実験液体キセノン検出器の2024年ランの運転状況および2025年ランに向けた取り組み” 飯山 悠太郎 “Real-time dynamics simulation of quantum fields on quantum computers” 吉岡 信行 “Error crafting in Mixed Quantum Gate Synthesis” “Symmetric Clifford twirling for cost-optimal quantum error mitigation in early FTQC regime” 中園 寛 “DarQ-Lamb暗黒物質探索実験: 超伝導量子ビットによる変調可能キャビティを用いた暗黒物質探索の展望” 小貫 良行 “銅導体よりも放射線を減弱・散乱させにくく、軽量で柔軟性に優れたアルミ導体の多層フレキシブル基板の開発” |
